「絵本=子供向け」という固定化されたイメージを傍目に淡々と邁進する絵本作家・長田真作。それが常識であったということに気づくためには、少しだけ角度のあるところから物事を眺める必要がある。
過ごしてきた環境や周囲との関係性によって後天的に人間の認識が育まれるものとすると、長田真作たらしめてきた構成要素とは一体何だったのだろう。捉えどころのない若い絵本作家の半生の伏線を回収していきたい。(取材・執筆:岩辺智博)

〈盟友〉
なだらかな丘に家々が建ち並ぶ東急田園都市線沿い。改札を抜けて坂を下り先にある住宅街の中のカフェ。ランチ営業開店の10分前に到着。その日、朝から降り続いた雨は少し前に止んだが、空は灰色に覆われている。店が開く頃に長田がやってきた。
「あいつとの出会いだけは、再現できないもの」(長田真作。以下、長田)
単独取材を予定していた当日、長田の盟友で俳優の満島真之介が突如カフェにやってくることを知る。
「彼、純朴ですけどすっきりしてますから。打ち合わせの時とか、よく隣にいますけど話はわかってないと思います。それも含めて別にいいなと思って。5ページくらい本読んだら寝ちゃう人だから。むしろ、そいうところが合わないから楽なんですよ」(長田)
一日中自室にいても苦ではないという徹底した思索派の長田と、生粋の行動派の満島。対局の生態が、絵本創作、役者という今に如実に反映されている。今でも週に6日は顔を合わせるという2人の出会いは10年前に遡る。

〈遊び〉
広島県呉市の高校を卒業した18歳の長田。進学するわけでもなく就職するわけでもなく姉の住む東京・三軒茶屋の部屋に転がりこんだ。上京の数日後、近所を歩いていた長田は掲示板のチラシを目にした。
「子どもと一緒に遊んでください!」というような内容だったらしいが詳しく覚えていない。求人内容そのものではなく、「なぜか引き寄せられた」。
勢いそのままに早速現場へ向かうと、施設長との簡単な面談を経て、その日のうちには子供たちに混ざって遊んでいた。それが「NPO法人・わんぱくクラブ育成会(以下わんぱくクラブ)」との出会いだった。
このNPOは障害をもつ子どものための「放課後クラブ」。何らかのハンディキャップを抱える小学1年生から高校3年生までが放課後にやってくる。
「スタッフというよりは、とにかく一緒に遊ぶ仲間。ぼくは穴を掘るのが好きだったので、ずっと掘ってましたね。『掘ろうよ!』なんて子ども達を誘ったことは一度もありません。ぼくが穴を掘ってると、隣に来て負けじと掘る子がいる。手伝おうとする子がいれば『俺のやり方があるんだから、お前は自分の作れ』と言ってました。他のスタッフからは呆れられてたけど、わんぱくクラブには一つのやり方やセオリーを押しつけるスタッフはいなくて、そこが良かった」(長田)

〈18歳〉
わんぱくクラブに長田がやってくる1週間前。やはり外に張り出していたチラシを見て「ふらりと」ここに入り、子ども達と「遊んでいた」のが18歳で沖縄から上京したばかりの満島真之介。今でこそ大河ドラマから映画まで幅広い役柄をこなす実力派俳優として知られる満島だが、上京当時から役者志望だったわけではない。
はっきりとした目的はなく、とりあえず上京した。そんな2人が意気投合することに理屈の介在する隙はなかった。
「仕事や学校、同じ趣味をきっかけにした出会いってその物事が終わっちゃうと関係も一緒に終息しちゃうんですよね。そういう出会いが一番多いと思いますし。一応ぼくたちも職場での出会いではありましたけど、ぼくらにとっては『仕事』と言っていいかわからない場所でしたし、はじめから関係性としては『よくわからないけど一緒にいる』くらいでしたし、今もそれは変わりません。理由とか理屈がないんです」(満島真之介。以下、満島)
10年間、もっとも多くの時間を共にしてきた満島はどんな言葉で友を形容するのだろうか。
「言葉で表そうとするとすごく難しい。その『難しい』っていうのがぼくたちの関係の答えなのかもしれないですね。他の人のことだったら説明できますから。『仕事仲間です』とか、『飲み仲間です』、みたいに」(満島)
「家族のようなものか?」という問いには、2人ともすかさず首を振った。
「親密さを『家族』と表現してしまうと、呉と沖縄にいるぼくらの家族はどうなってしまうのか、という話になるので(笑)」(長田)

〈純度〉
「あの5年間で世の中のほとんどすべてのことを語れるといっても大げさじゃありません。それくらい、すべてを体験した時間でした」(長田)
長田が言っているのは、わんぱくクラブで過ごした時間のことだ。長田や満島の在籍していたわんぱくクラブ三軒茶屋支部には、自閉症、多動症、ダウン症をはじめとした子ども達が、世間では「障害児」「障害者」として呼ばれるわけだが、一人ひとりの子どもは多様だ。
長田と満島はわんぱくクラブの子供たちのことを「スター」と呼ぶ。
「デカルトの言葉に『我思う、故に我あり』ってあるじゃないですか。わんぱくクラブの子供たちってこれを一番実践してると思うんです。『我食う』とイメージしたらもう食べてますし、『我言う』となれば、もう言ってるんですよ。とても純度の高い存在じゃないですか」(長田)
我食う、故に我あり。
「もちろん、注意しないといけないこともあります。休日に一緒に出かけて、電車が好きな子は駅で黄色い線を超えて電車に向かおうとしちゃうんですよ。そういうときだけです。厳格にストップをかけるのは」(満島)
何らかの障害を持つ子供たちの動きは不可解に見える。近くで眺めていても、何をしたいのか理解することは難しい。それは彼ら自身にも説明できるものではなく、おそらく何を考えるでもなく、したいと思ってしまった動きをしようと試みているのではないだろうか。
「世間一般では特別支援学級や福祉って言うと、『普通の学校に進級させよう』とか、『将来どこかの職場で働けるようにしよう』とか、マイナスをゼロにすることから始まってる。だから暗いんです。ぼくは『あー、そうじゃないんだよな』って思う。素晴らしいものってそのままの状態が一番いいんじゃないかな。『この子にそれができてどうするの?』っていうようなことがたくさんあります。『箸が持てるようになったね!みんなで拍手』とかしてる場合じゃないんです。唯一無二な彼らが生きているっていう事実がすでに素晴らしいんですから」(長田)
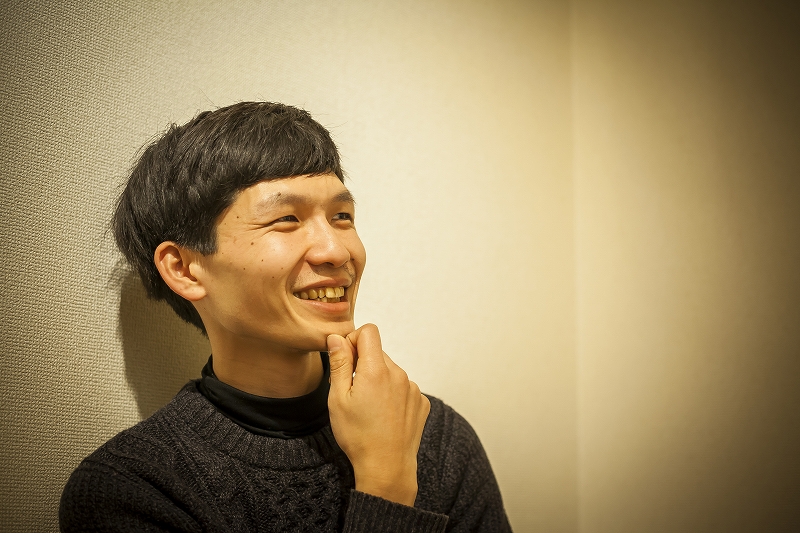
〈子供〉
交通量の多い三軒茶屋駅近くの商店街。一本裏手に入ると、複合施設の1フロアに「わんぱくクラブ育成会三軒茶屋支部」がある。現在、施設長を務める中村美由紀は長田や満島の約半年後にアルバイトとして加わった。長田とは4年強の時間を共に過ごした。
「男性スタッフは今も昔も少ないです。2人はダイナミックに遊んでくれた貴重な存在でしたね」(中村美由紀。以下、中村)

長田や満島が離れてから2度移転したという三軒茶屋支部だが、長田が子供たちに描いた100枚以上の絵が、大切にラミネート加工されて今も残っている。わんぱくクラブに通っていた子供たちを登場させて、コミック調に仕上げたアンパンマンのパロディなど。現在の長田の作品とは別の遊び心に溢れている。
「長田さんは、自分からかがみ込んで子供に目線を合わせるというやり方ではありませんでしたね。子供が楽しい遊びを素のままで一緒にできてしまう。1日1日でやることが全然違っていて。習慣はあんまり作らないタイプでした」(中村)

わんぱくクラブ三軒茶屋の取材後、久しぶりにわんぱくクラブを訪れたという卒業生とその母親にわんぱくクラブと長田の記憶を聞くことができた。
「特別支援学級にいると歌って童謡ばかりなんですけど、わんぱくクラブに行けば流行りのJ-POPを教えてもらえるんです。スタッフと子供ではなく、本当に友達のように一緒に遊んでくれたのがわんぱくクラブにいた長田さんのイメージですね」(卒業生の保護者)
長田の母親は、特別支援学校の教諭だった。だから長田は少年時代からハンディキャップを持つ児童を目にすることはあったが、特に思い入れがあったり福祉に興味があったわけではない。わんぱくクラブでアルバイトしたことは本当に偶然。実際に子ども達と関わりを持つことで彼らの魅力に魅せられていくことになる。
「別に子供が好きってわけじゃないんですよ。障害のある子供だったから良かったと言うと変かもしれないですけど、彼らとは気が合うんです」(長田)
通常、コミュニケーションでは相手を慮ったり、ときには出し抜こうとしたりするものでもある。そうした場合、メッセージを受けて返答するまでに少しだけ考える間が生じるもの。長田は、わんぱくクラブの子供たちにはそれがないと言う。彼らは論理やロジックの外にいるのだと。多くの人が学校や会社で過ごす中で失っていくカオスな感性、「混沌」をそのまま保持している存在なのだ。
「30人いたら、それはもう30カ国、30の星なんですよ。そのくらい子供たちはそれぞれ違いますし、個人の内側に広大な宇宙が広がっていることを見せてもらいました。わんぱくクラブで過ごした5年間の日々で、『個人の可能性』という実感が確信に変わって、今のぼくの創作にとてつもない大きな影響を与えています」(長田)

〈世間〉
満島は役者を志し、長田が五味太郎との出会いをきっかけに絵本作家の道を進むためにわんぱくクラブを離れてからも、2人の関係が終わることはなかった。それぞれの領域で実力を積み上げ、今では2人がスピーカーのトークショーにも多くの人が集まるようになった。
「サク(長田)は絵本をたくさん出して、ぼくも出演が増えてきた。知名度が上がるといろんなことができると言われますけど、ぼくは真逆だと思うんですよ。ただ業界内で扱いやすいターゲット候補に入ってきたということに過ぎないんです」(満島)
私(著者=岩辺)は一瞬考えた。2人は大きな体制に反感を持っているのだろうか。しかし、2人の話は意外な軌道を見せる。
「ぼくたち、意外と古い体質なんです。だからメジャーな舞台で勝負しなきゃ意味ないと思ってますよ。ただそれは業界の方を向くという意味ではなくて、作品にとことん向き合うことで結果を出していくということです」(長田)
「同年代の人たちが既存のフィールドから外したところで色々なことを始めてますけど、ぼくたちは伝統的なものに入っていくんです。そこで都合よく使われる存在になるんじゃなくて、自分たちも曲がらない。包んでください、ぼくたちも包みたいので。そんな気持ちで戦っています」(満島)
それぞれの業界で頭角を現しはじめた2人の関係は、決してプライベートにとどまらない。長田の出版記念イベントに満島がゲスト参加したり、満島がインタビュアーを務める誌面ではデザインを長田が担ったりしている。それぞれの分野をクロスさせることで世の中の袋小路を打開できるということにも気づきはじめた2人のコラボレーションは今後さらに加速するだろう。
社会や業界に対してギラギラと反抗するわけでもなく、といって従順にへつらうわけでもない。長田は、世の中や外部と調和を図ることは、わんぱくクラブでは当たり前の日常だったと言う。
「わんぱくクラブの子ども達は、自分だけではうまくできないことが多くて、それに対して厳しい眼差しを向ける世間がある。彼らやその周囲が、彼らの素晴らしさを守りながら、世間を渡っていくことは相当エネルギーが要る」(長田)
ここまで終始和やかな雰囲気で語ってきた長田の表情が引き締まるのを見た。言葉にすることは、実行することに比べて難しいことではない。

〈目標〉
「久しぶりに目標ができたんです。ぼく、“澄み切った単細胞”になりたいなと思って」(長田)
“単細胞”と聞けば、少なからずネガティブなイメージを抱かれる。しかし、長田は言葉の解釈を簡単に他者に委ねたりはしない。
「“単細胞”って実は最強なんじゃないかと思ってるんです。人は複雑なことを過大に評価しますよね。苦境を避けるためにすぐに逃げたり、欲望に迷いなく素直に従える“単細胞”という力。これって、何をするにも懸念が先行して身動きが取れなくなっている今、最高の性質だと思うんです」(長田)
上り坂を邁進する新鋭の絵本作家が志向する「澄み切った単細胞」。その言葉に長田が込めているものは何だったのか。その少なくない構成要素としてわんぱくクラブでの日々があることは疑いない。
次回は長田の基軸を紐解く上で切り離すことのできない生まれ育った街、広島・呉、そして堅牢な個人主義を形成するきっかけとなった父の存在について取り上げたい。
(敬称略)
《関連記事》
【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作〜第1回 混沌としたピュア〜
【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作〜第3回 奔放な遺伝子〜
【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作〜第4回 共振する鼓動〜(最終回)
追記:2018年11月5日:長田真作さんの新作が発売されました。作品名:『なりたいのは』(絵本塾出版)
追記:2018年12月1日:朝日新聞2018年11月30日夕刊「私の描くグッとムービー」に長田真作さんのイラストと記事が掲載されました。「私の描くグッとムービー」は、画家、イラストレーター、漫画家、絵本作家などビジュアル表現に関わる芸術家やクリエーターが、思い出の映画について語るとともにその映画を一枚の絵に描くというコーナー。
長田 真作(ながた しんさく)
1989年、広島県呉市生まれ。2016年、絵本作家デビュー。主な作品に『あおいカエル』(文・石井裕也/リトル・モア)、『タツノオトシゴ』『コビトカバ』(以上、PHP研究所)、『かみをきってよ』(岩崎書店)、『きみょうなこうしん』『みずがあった』『もうひとつのせかい』(以上、現代企画室)、『ぼくのこと』(方丈社)、『風のよりどころ』(国書刊行会)、『すてきなロウソク』(共和国)など。ファッション、映像などとのコラボレーションでも活躍中。

取材・執筆:岩辺智博(いわなべ ともひろ)/1993年生まれ。愛知県豊橋市出身。中央大学卒業後、大手旅行代理店、温泉旅館、農家、自動車工場と職を転々。その後、フィリピン総合情報サイト『Phil Portal』にてライティング・編集担当。25歳を機にフリーライターに転身。ブログ「さぐりさぐり、めぐりめぐり」運営。Twitter@tomotaro0106
撮影:樋宮純一(トップ画像とクレジット記載の写真)
企画・取材・編集:石原智
掲載:2018年5月掲載












