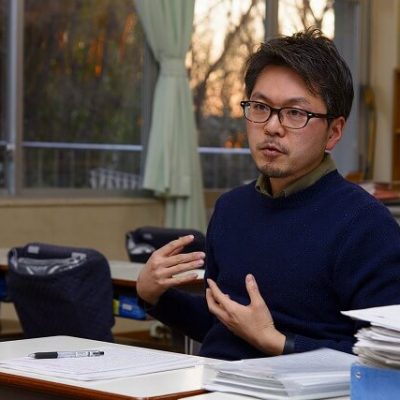企業経営には、ビジョンやミッションが必要である。ビジョンは、企業の未来をしめす。ミッションは、企業が社会に何をもって貢献するか、存在意義に関わる。ここまでは多くの経営者が理解し、実践している。ところが企業経営にフィロソフィ(哲学)が必要といえば、「おおげさな」「きれいごとで経営はできない」などと反論があるかもしれない。しかし企業の社会貢献(CSR)が浸透し、持続可能な開発目標(SDGs)が掲げられる時代、逆にフィロソフィのない企業が存在できるかという疑問もある。サラヤ株式会社の事業と経営姿勢は、企業に流れるフィロソフィについて、考えるきっかけになるかもしれない。

サラヤ株式会社 更家悠介(さらや ゆうすけ)代表取締役社長。1951年生まれ。1974年大阪大学工学部卒業。1975年カリフォルニア大学バークレー校工学部衛生工学科修士課程修了。1976年サラヤ株式会社入社。取締役工場長を経て1998年代表取締役社長に就任、現在に至る。1989年日本青年会議所会頭、地球市民財団理事長などを歴任。NPO法人ゼリ・ジャパン理事長、ボルネオ保全トラスト理事などを務める。
SDGs,CSR……地球、社会の中での企業活動を追求
社会的な課題をビジネスの手法で解決する「ソーシャルビジネス」の優れたアイデアを表彰する「第1回 日経ソーシャルビジネスコンテスト」(日本経済新聞社主催)の表彰式と記念シンポジウムが、2018年3月3日に日経ホールで開催された。
記念シンポジウムでは「SDGs(持続可能な開発目標)時代のソーシャルビジネス~これから企業に求められることとは~」。国連による社会課題解決の目標「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」が注目される中、企業が果たすべき役割をテーマに議論を展開した。
そこに登壇したサラヤ株式会社の更家悠介社長は、受賞者に「みなさんの応援団になりたい!」とエールを送り、社会貢献型企業として注目される同社の社長らしいメッセージを発信した。
「お金を暴力的に使っていると、いつか地球の資源が枯渇してくる。経済が持続可能であるか。富が偏在化せず、きちんとした生活ができるか。ビジネスをする社会そのものが持続可能であるか、それが問われています。ビジネスをする人を支える地球や環境が持続可能でなければならない。
2015年に『SDGs』というものがでてきました。企業としては、ビジネスを通じて持続可能性を実現しよう。人を巻き込み、投資家を呼び、人を育成しようということですが、みなさんにも、ぜひそれを目指していただきたい。
サラヤは自己検証しながら、SDGsを社内に位置付けています。たとえば東南アジアのボルネオ島で、NPO活動をやってきました。ウガンダでも、最近ではエジプトでも進めています」
サラヤは、2017年に開催された日本政府による第1回「ジャパンSDGsアワード」で「SDGs推進副本部長(外務大臣)賞」を受賞。「100万人の手洗いプロジェクト」として、商品の出荷額1%をアフリカ・ウガンダでのユニセフの手洗い普及活動の支援に当てていることなどが評価された。
サラヤは、SDGs推進にとどまらず、CSR(企業の社会的責任)など、「企業と社会」を考えるときに真っ先に思い浮かぶ存在だ。規模で言えば、グループ従業員数約1800人、売上高約400億円。一般的にはそれほど大きな企業とは言えない。しかし、これからの企業像を体現し、世界から求められる存在となっている。その真源を探ってみたい。

赤ちゃん用の「アラウ.ベビー」シリーズ。サラヤらしい無添加の製品。
持続可能性の訴求は「きれいごと」か
ビジネスを展開する上での経営資源は「ヒト・モノ・金(カネ)・情報」。どんなメーカーも、煎じ詰めれば地球にある資源を有効に活用することで、商品をつくり販売している。石油はその代表だ。それゆえ企業には、地球にある資源を効率的かつ持続的に活用しながらビジネスを続ける使命がある。
ビジネスを展開するベースである地球には、様々なな課題が露呈している。
「大地をみれば、窒素分が多すぎる。土地に肥料をやりすぎて逆に劣化してきている。これまで持続可能だと思われてきた土も、その持続可能性がなくなってきている。やっぱりビジネスも生活も、現実に対して何がしかのソリューションとまではいかないけれど、方向感覚がないと、いつかはうまく回らなくなってしまうでしょう」(更家社長)
日々ビジネスで苦労している経営者は、「きれいごと」という言葉をネガティブに使うことが多いのではないか。
曰く、「ビジネスは、きれいごとだけじゃすまない」。
あるいは、「フィロソフィ(理念・哲学)で飯が食えるか」と。

ヤシノミ洗剤シリーズ。1971年の誕生のロングセラー商品 本社には歴代のパッケージが展示されている。
ソーシャルビジネスの重要性はわかっていても、それが売上や利益につながるのだろうかという懸念もある。
そうした中で、サラヤの事例をみれば、企業経営において、地球環境や社会課題の解決が本質的なことだということがわかるだろう。
確かにサラヤは、特別な才覚を持ったオーナー創業者とそれを引き継ぎ拡大させた二代目経営者がつむいだ「特別な事例」なのかもしれない。
とはいえ、「特別」という言葉が消え、同様の事例が続々と出てくる時代は来ている。成熟市場の消費者は、似たような商品ならばフィロソフィの感じられる「顔の見える」商品を買う。企業は、自社の取引構造(サプライチェーン)に関わる事業者にサステナビリティ報告書を求める。フィロソフィがない企業が持続可能なビジネスを展開することは難しくなっている。
「経営判断は、いつも難しいものです。迷ったときは、私は自分たちの原点である企業理念に照らします。進んでいく方向が同じかどうか。もし方向が一緒ならば、歩きだすことになる。そして歩きながら、プロジェクトを進めながら売上と利益を考え、じっくりと修整をかけていく。一気に多額の投資はできませんが、新たな価値を生み、誰も手掛けたことのないブルー・オーシャンに漕ぎ出すのを恐れる理由はありません」(更家社長)
創業当初から、サラヤは環境にも人の肌にも優しい天然の植物油脂を使った製品を作り続けてきた。同社の微生物に分解される性質をもつ商品は、排水の汚染予防にも役立ってきた。その代表が看板商品「ヤシノミ洗剤」。
また、いまではどこでも見かける「アルコール手指消毒剤」の普及にもサラヤは貢献している。
海外では本業の衛生事業だけでなく、「ヤシノミ洗剤」の原材料であるパーム核油の主要な生産現場となっていたボルネオ島で、環境保全活動に積極的に取り組んできた。

手指衛生商品。医療や食品衛生などプロ用衛生でのノウハウを一般向けに活かす。
企業文化「清流の感覚」を襲った危機
サラヤには「清流の感覚」という企業文化がある。
清流は、日本の山間のいたるところで見られる原風景であり、それは「無理のない、無駄のない、汚れのない、きれいな水の流れ」である。サラヤは清流のように「無理のない、無駄のない、汚れのない生活の役に立つ製品を提案するとともに、企業としても清流のように、大河とは異なるが小さくとも澄んだ川のような企業でありたいと願ってきた。
ところが、一点の曇りのない清流のような経営を続けてきたと自負していたサラヤが一転して、「生態系を破壊させる企業の一つ」としてテレビ番組で紹介されるという危機を迎えることになる。
2004年、あるテレビ局からの電話は、更家社長には晴天の霹靂(へきれき)だった。
環境に優しい製品が森林を壊す?!
主力製品「ヤシノミ洗剤」の主な原料であるココヤシの油とパーム核油(アブラヤシの種から搾った油)は、石油系の油脂と比べて人の肌に優しく、排水が微生物に分解されやすい。それゆえ自然に優しい製品として消費者に支持されてきた。
その信頼が崩れかねない自体が発生した。
2004年、更家悠介社長に、テレビ朝日系列で放送されていた「ステキな宇宙船地球号」というテレビ番組担当者から出演の申し入れがきた。環境問題についてコメントがほしいという。
「社長、ご存知ですか?」
「ご存知って、何を?」
「パームオイルのプラントを作るため、ジャングルが破壊され、その伐採が森林に住むゾウやオラウータンを殺しています」
担当者の話を聞いた更家社長は、「そんなことがあるのだろうか」という違和感につつまれていた。
東南アジア3カ国にまたがるボルネオ島で、パーム核油の原料であるアブラヤシ栽培のプラントのせいで、野生動物の住む森林環境が破壊されている。とくにボルネオゾウという世界最小の野生ゾウが、プランテーションの拡大で危機に瀕していた。
アブラヤシの油は、食品や洗剤など幅広い商品に使用され、世界的に需要が増えてきていた。東南アジアの熱帯地域でもよく育つので、急速にアブラヤシのプランテーション(大規模農場)が拡大している。
問題となったボルネオ島でも、プランテーションによって熱帯雨林が減少し、ジャングルに生息していた野生動物たちの行き場がなくなってきたという。

ワナにかかり傷ついた子ゾウ(サラヤ ボルネオ環境保全プロジェクトページより)
ボルネオ島の悲劇
森林を追われたボルネオ島のゾウゾウは、食料を求めて農園に侵入せざるを得ない。
農地には、農作物を荒らすイノシシやシカを捕獲するためのワナをしかけられている。ジャングルを追われた子ゾウがワナにかかり、重傷を負うことが頻発していた。
番組スタッフは真剣だった。「私が現地に行って確かめてきました」。
テレビ番組では、ワナのロープが脚に食い込んだままキズが治らない子ゾウ、長い鼻がちぎれそうになっているゾウが放映されるという。
自然に優しいと信じていたサラヤの製品の原材料の生産現場で、ゾウをめぐる森林環境が失われているなどとは、サラヤの人たちは夢にも思ったことがなかった。もちろん一般消費者も知らない。
そのような状況で、TV番組で、環境破壊の原因をつくったアブラヤシの油を使う立場として登場する企業があれば、視聴者はどう感じるだろうか。
「企業ブランドが、大きく傷つく危険性がありました。場合によっては不買運動に発展するかもしれません」(更家社長)
アブラヤシの油を使っている他社は、すべて、テレビ局からの出演依頼を断ったという。だが、逡巡はあったが、サラヤはテレビ取材を受けた。

2004年、ボルネオの現状を知り、他社が断る中でテレビ出演
目を背けず、現地に赴き、本質的な解決を目指す
テレビカメラの前で、更家社長は「こんなことがあるとは知らなかった。驚いています」と率直に、そのときの気持ちを語った。
2004年8月、テレビ番組を観た視聴者の反響が伝わってきた。全般的に抗議する内容が多く「ゾウがかわいそう」と電話で訴える人もいたという。「パーム核油を使うのを止めたらいい」という提案も多く寄せられた。 「環境破壊があるとわかってもなお、パーム核油を使い続けるなら、サラヤの企業姿勢が問われる」との指摘もあったという。
しかし、サラヤには、ボルネオ島で起きている問題の解決策として、単純にパーム核油を使うのをやめることをとるわけにはいかなかった。それでは問題の本質を解決したことにはならない。
“青天の霹靂”の後、更家社長は、すぐに社員をボルネオに派遣した。現地調査を進めて、わかったことがあった。
パーム油は、大部分が揚げ油、マーガリン、チョコレートなどの食糧として消費されている。しかも、最も安い植物油脂の一つ。もしパーム油をつくらなかったら、困るのは先進国の住民ではなく、貧しい国の消費者だ。パーム油を作らなくなったら全世界の食料需要を満たせなくなるからだ。
先進国ならば、パーム油より高価な油を使った食べ物を購入して生き残ることができるが、貧しい国では無理だ。先進国がパーム油の生産をやめても、森林環境保護の代償として、低所得で貧しい人々の食料を奪うという結果を生むことになる。同時にパーム油の生産をする国の人々の仕事を奪うことにもなる。
世界は、根本的な解決策を必要としていた。
※パーム油生産量は2005年に大豆油を抜き、世界で最も消費されている植物油となる。
”青天の霹靂”から素早い対応
パーム油を使う他社が尻込みする中、番組に出演したサラヤにとってマイナスの反響があったことは、番組制作者にとっても不本意な結果だった。視聴者にサラヤの企業姿勢を誤解されてしまうのは忍びないと。
そこで番組では同じテーマを2005年3月に再び取り上げ、パーム油生産に関わるボルネオ島での環境問題について事実を知ったサラヤが進めてきた取り組みを紹介した。
”青天の霹靂”のあとのサラヤの動きは早かった。例えば、2005年1月にはマレーシアのクアラルンプールで行われた「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」と呼ばれる国際組織に参加。アブラヤシのプランテーション開発について環境保全活動を行うことを表明。この活動には、ボルネオゾウの保護活動も含まれる。
RSPOは、パーム油(アブラヤシ)の生産から販売まで、パーム油の流通にかかわる誰もが加入することができ、環境や社会に悪影響を与えない良いパーム油を作り出していこうという集まり。サラヤは日本に籍を置く企業として初めて加盟し、環境に配慮したパーム油産業のルールづくりに取り組み、RSPO認証(パーム油)制度の普及に努めている。
熱帯雨林の危機を知ってから1年弱でのサラヤの迅速な対応を見た視聴者からは、非常に好意的な反響が寄せられた。

2005年1月にゾウの救出移動用車を寄付。現地に調査員を送り、探索、捕獲、治療を行い、現在も活動を継続。(写真提供:サラヤ)

ボルネオには更家社長も何度も足を運んでいる。2013年には「ボルネオ象・レスキューセンター」が完成。(写真提供:サラヤ)

ボルネオ象・レスキューセンターで保護されたゾウ(写真提供:サラヤ)
熱帯雨林の回復を目指す「緑の回廊」計画をリード
翌2006年2月、ボルネオで開催された「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム(BBEC)」で、サラヤは緑の回廊構想を提案し、賛同を受けることになる。
サラヤをはじめ、現地の国際協力機構JICA(独立行政法人国際協力機構)などが中心となって、2006年12月にボルネオ島にボルネオ保全トラスト(BCT=Borneo Conservation Trust)事務局を設立。現在、サラヤではNPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン(BCTジャパン)を通じて、現地の活動を支援している。
サラヤは、BCTをつうじてパーム油生産のためにアブラヤシ畑として開墾地を買い戻して森に再生し、熱帯雨林を一つに結ぶ「緑の回廊」計画を推進。BCTが土地所有権を取得し、それを支援した団体に土地命名権を与えている。サラヤが取得した「サラヤの森」も、現在6カ所まで広がっている。
| 取得年月 | 土地名 | 面積 |
| 2009年5月 | サラヤの森1号地 | 2.2ha |
| 2010年1月 | サラヤの森2号地 | 4.0ha |
| 2010年3月 | サラヤの森3号地 | 1.8ha |
| 2011年6月 | サラヤの森4号地 | 2.1ha |
| 2012年10月 | サラヤの森5号地 | 1.9ha |
| 2017年4月 | サラヤの森6号地 | 4.25ha |
消費者の環境への思いをつなぐ仕組みづくり
「ボルネオでゾウの保護園をつくったり、恩返しプロジェクトを回したり。そうしていくと、お客様が環境問題で、サラヤはこういうことをやっている。環境にいいと言ってくださるお客様もおられる。お客様から1%のお金をいただいているので、それを現地に真面目にお届けしています」(更家社長)
サラヤは2007年から「ヤシノミ洗剤」の売上の1%を、BCTによる「緑の回廊」計画に還元している。2012年からは「ハッピーエレファント」「ココパーム」、2013年からは「アユルスパ」ブランドも支援商品に加えられた。
サラヤの活動を通じて、日本で暮らす消費者も「Green Palm認証」や「RSPO SCCS認証」を受けたサラヤの製品を購入することで、ボルネオの環境保全に参加できる仕組みとなっている。サラヤが寄付をするというのではなく、サラヤの商品を通じて消費者が寄付をするということで日本とボルネオをつなぐことが重要なのだ。サラヤは、この活動の結果を社会に開示し、消費者には熱帯雨林の問題を「自分ごと」とする契機を提供する。環境活動は一企業だけではできない。消費者を含む広く世の中全体で取り組むものだ。

環境や社会に配慮して生産されたパーム油の認証を受けた商品(写真提供:サラヤ)
「持続可能性という価値観なら、どの国や地域とも共有できるかもしれない。けれど最初からビジネスプランとして考えるのは難しいと思います。まずはビジョンが一致したら、私は現地に飛びます。そこで修整する」(更家社長)
ボルネオが抱える環境問題は、パーム油を「つくる」ことが問題ではなく、無秩序に森を切ってアブラヤシ農園を開墾している「つくり方」に問題があった。
根本的な解決のためには、生産者をはじめ、パーム油に関わる皆が共通の問題認識を持って取り組む必要がある。そこでサラヤは「環境と動物と人に配慮されたパーム油」の生産と流通の仕組みづくりを行った。

天然酵母を活用した洗剤「ハッピーエレファント」シリーズ。地球と人体に最大限配慮された商品。ネーミングからも同社の思いが伝わる。
社会活動に参加するメリット
環境問題に限らず、サラヤが様々な社会活動を続ける理由は何か。
まず、社員が社会貢献活動に参加することで、世の中の困りごとにダイレクトに接することができる。そうすると、ビジネスの視点では見えないことが見えてくる。ボルネオで森を追われるゾウの姿が現在のサラヤには見えている。そして、それを解消するための行動につなげる。そこでの問題発見力や行動力、組織構築力は、商品開発や営業活動、広報活動にも反映される。
「これからは、ただサラヤの商品を買ってくださいと訴求するのではなく、会社そのもののもつフィロソフィが問われる時代になると思います。ユーザーに気に入られたい、役に立ちたいという顧客ニーズに対応するだけではなく、社会全体に対するフィロソフィが問われる時代に近づいています。企業としての社会のポジショニング、企業の向かう方向性が、問われることでしょう。サラヤの社員が現地の人々と一緒に活動し、ともに苦しみ、ともに喜べば、本当の笑顔でありがとうと言われる日が来ると信じています」(更家社長)
世界とつながる、フィロソフィの輪
社会活動が、意識の面だけでなく実際に事業につながるケースも多い。
更家社長には、ひっきりなしに「会いたい」というアポイントメントが入る。取材日の翌週には、カンボジアに飛び、香港在住の日本人の経営者と会う予定だという。
その経営者は魚の養殖をやっている。その魚はエサから肉への転換率が非常に高いという。アフリカが原産地で、半年で大きくなる。それを切り身にしてフィレをつくり、急速冷凍技術で凍らせて流通させる計画だという。世界的な漁獲競争への一つの対策になるかもしれない。サラヤは、製造段階で工場の衛生環境を整える仕事を担当する。
サラヤの本質は変わらないが、「環境保全」「社会課題解決」といったフィロソフィを共有できるパートナーが世界中に広がっている。
「ビジョンに照らし合わせ、軸がブレなければ進めていきたい。そのときも進みながら調整していきます。行動していくスピード感が必要です。事業として伸びればいろいろあるかもしれませんが、今は大きな投資ではなく、できる範囲で進めています」(更家社長)
そんなサラヤ社長が次世代に遺したい価値は何だろうか。それは持続可能な環境そのものだという。
「次世代に遺すものは知恵というソフトも大事ですが、まず生物として生きられる環境です。企業も、空気をきれいに保つ努力をしなければなりません」(更家社長)

本社応接には、プリミティブな力を感じさせてくれる絵画が掲げられている。
”衛生”という市場を広げる
サラヤの創業は、1952年にまでさかのぼる。
1945年8月の終戦から7年目。その頃の日本は衛生環境が整わず、集団赤痢や集団食中毒が多発していた。実際、戦後日本の赤痢患者のピークは1952 年で、11 万人を超えている。固形石鹸はあったものの、日本ではまだ液体の「石鹸液」は売られていなかった。
サラヤの創業者である更家章太氏は、高度成長期に向かう黎明期の日本で消毒剤を配合した薬用石鹸液、および専用ディスペンサーを業務用として発売。これは当時の日本の花形産業であった繊維工業や鉄鋼業、学校、官公庁などで次々と採用されたという。

1952年創業。手洗いと同時に殺菌・消毒のできる石けん液と「押出・押上式」容器を工場や学校に普及させた。当時の精神は、現在のアフリカなどでの衛生事業にも息づいている。
さらに工場などの社員食堂で大規模な食中毒事故があり、企業の給食施設の手洗いへと事業が拡がった。この市場は競合がないブルー・オーシャンであり、さらに医療衛生にも市場を拡大していく。
しばらくは法人需要に特化していたサラヤは地力をつけ、競争の激しいレッド・オーシャンの一般消費者向けの市場に参入する。そこには水質汚染という社会問題が背景にあり、それを解決したいという創業者の強い思いがあった。
レッド・オーシャンのなか、社会問題へのソリューションという「ブルー・ストリーム」になったのが自然派のサラヤの「ヤシノミ洗剤」だ。
その当時、河川が泡立つ問題が発生していた。とくに琵琶湖の淡水赤潮なども、家庭から流される合成洗剤が主な原因とされた。滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例が公布されたのは1979(昭和54)年10 月17 日。その4日後の21日に「ヤシノミ洗剤」を発売した。
この「ヤシノミ洗剤」が大手の追随商品による価格競争にも生き残ることができたのは、「手洗い石鹸液」で磨かれた手肌へのやさしさの技術と、すすぎ性の良さによる。「ヤシノミ洗剤」は水に拡散しやすいのが特長で、食器や野菜果物に洗浄成分が残りにくい洗剤であった。
今日、サラヤは公衆衛生から食品衛生、病院内の衛生まで、あらゆる衛生関連事業を手がけている。しかも日本初、世界初というチャレンジが多い。
もともと「衛生・環境・健康」に関わる事業に国境はない。医療分野では、医療器具の洗浄機や哺乳瓶などの滅菌・消毒機を、食品分野ではフリーザーや電解水の精製装置などを開発している。
サラヤの事業が秀逸なのは、それらの事業を単独で行うのではなく、その国の経済発展に寄与できるかどうかという観点も併せ持つ点だろう。これまでにも、アフリカ・ウガンダでの製品の現地生産をはじめ、中国やボルネオ島での、安心・安全や環境に配慮した原材料の生産などを実施してきた。
今後はこうした動きを、ミャンマーからベトナム、フィリピン、インドネシアなど東南アジアの各国に広め、食品や公衆衛生を啓蒙していくとともに、サプライチェーンの強化を図っていく予定だという。

かつてあったコインを入れるタイプのうがい機。うがい機の普及もサラヤの貢献が大きい分野。
原点にあるのは”清流”
サラヤの原点はどこにあるのか。
サラヤ創業者は、現社長の更家悠介氏の実父である更家章太氏。生家は、三重県熊野市で代々林業を営んでいた。
熊野は日本古来の宗教・世界観のルーツであり、太古の自然が息づく日本の原郷。創業者は、この熊野の山奥で清流の鮎や鰻、川海老を捕り、豊かな自然の恵みに育まれて成長した。父母の山へに対する愛着と、自身の熊野川の思い出が創業者の心の奥深くに残った。

創業者更家章太氏。本社内に掲示されているインタビュー記事。
創業者は、いつまでも熊野の清流をめぐる自然観や生活観を忘れることなく、自然にやさしい商品開発に取り組んだ。これはサラヤの事業の原点として位置づけられ、企業のDNAとして今もしっかりと受け継がれている。
「日本の渓流は、世界でも、あまり見ないものです。独特の風景ですから、それは残したい」(更家悠介社長)
近年、地球温暖化の影響もあり、日本各地で大水の被害が広がっている。山に植林はするものの、土のメンテナンスができていない。清流のある自然は、意識的に守っていかなければどこかで破壊につながる危険性がある。
都市部と違って里山は、ビジネス価値があるとは限らない。従来の尺度ではない、売上や利益率ではない視点での開発が必要なのかもしれない。
「私たちの活動は、ふつうの経済的な尺度だけでは測れません。もちろんビジネスなので売上と利益は上げないといけません。もともとアンビバレンツなところがあるわけです。それは人生も同じです。そういうところは押さえた上で、ビジネスとして回っていけばいいと思います」(更家社長)
更家社長は、自社のDNAを「熊野川の清流で育った自然観」と表現する。
「汚れを清めること」、「自然に無理をかけないこと」、「無駄を出さないこと」。清流のイメージとも重なるこの感覚は、山が多くて水に恵まれた日本の風土では、とても身近な存在。この清流の性質によく馴染むような“自然観”が、サラヤには受け継がれている。

本社社屋(大阪市東住吉区)
創業者と映画青年の出会い
ここで、サラヤの創業者更家章太氏と、現社長更家悠介氏をつなぐ人物に登場していただこう。サラヤ株式会社取締役コミュニケーション本部本部長兼コンシューマー事業本部副本部長の代島裕世氏。社長を支え、サラヤの社会活動を推進している責任者。
「初代はモノづくりが大好きで、開発ひとすじ。何につけてこだわりが強い。広告文もすべて自分で校正する人でした。根っからのクリエイター。パッケージについては削りだした1ミリまで自分で確認しなければ気が済まない。自分の手元にイラストレイターとグラフィックデザイナーを置き、毎日呼んで修整を加えていました」(代島取締役)
いまから20年以上前。29歳の代島さんは、タクシー運転手をしていたときにサラヤ創業者と出逢い、サラヤに”スカウト”された。
代島さんと、創業者・更家章太氏の出逢いは次のような偶然だった。
1995年の春。昼過ぎの東京・品川。代島さんはタクシー運転手として、毛皮のコートを着た品のいい老人を乗せた。「会社の登記について調べたいから、関連書のある場所で降ろしてくれ」と言われた。代島さんは、東京駅前の八重洲ブックセンターに向かった。しばらく走ると、後部席から、「若いのに何でタクシーの運転手をしているのか」と声がかかった。
その当時、若いタクシー運転手は少なかった。代島さんには子どもが生まれたばかり。このままタクシー運転手でいいのか悩んでいた時期でもあった。
「食べられないからです」
「何で食べられないの?」
「ぼくはドキュメンタリー映画を撮っていまして」
そんなやりとりが続いた後、乗客が「キミは大学を出ている?」と聞いた。

サラヤ株式会社 代島裕世(だいしま ひろつぐ)取締役。1965年3月14日埼玉県生まれ。二人の経営者の側で仕事をしてきた。
当時のサラヤの社員は500人ほど(現在は1500人超)だったが、大卒の採用に苦労していた。特に新卒での大学出身者の採用に苦慮していた。
「一応、早稲田を出ています」
「ゆっくり話をしたい。タクシーメーターを上げたままでいい。喫茶店に入ろう」
新橋あたりで駐車場に入れ、タクシーのメーターを倒したまま喫茶店に入った。
乗客が「オレは社長で、ヤシノミ洗剤をつくっている」と自己紹介。
そこで代島さんはハッとした。その洗剤を、彼は下落合のスーパーで見かけていた。ステンドグラスのデザインで、日本語がまったく書いてないパッケージが気に入って買ったものと同じだった。反射的に、「それ、使ってます」と答えた。
代島さんが、一生の仕事と出逢った瞬間である。
その数日後、自宅にサラヤの会社案内と商品見本が送られてきた。社長の秘書から何度か電話も来た。
そのうち「大阪まで面接に来てくれ」となった。
そこで「ボクには妻と赤ん坊がいるので行けない」と答えると、「家族全員、大阪に連れて来い」と言う。
東京-新大阪間の新幹線のチケットが二人分、送られてきた。そこで赤ちゃんを実家に預け、夫婦二人で大阪まで面接に向かった。
新大阪の駅、改札を出たら社長が待っていて、そのまま料亭に連れていかれ、お昼を食べた。もう後には引けなかった。
サラヤという”ドキュメンタリー作品”
出勤すると社長の部屋に行き、夕方まで社長の話を聞いた。毎日同じような話だけれど、面白かった。やがて商品のデザインや広告を任される。CM制作では、いきなりコピーライターもやらされた。サラヤの広告をサントリーや資生堂のようにしたいと社長から言われた。
1998年、現社長の更家悠介氏が社長に就任し、創業者は会長になった。世間一般でいう「二代表制」で、会長も社長も、ともに代表取締役となった。
代島さんは、仕事中、同じ案件を社長と決め、会長と決め、根回しをする。会長からは「社長の部屋に行ってから、オレの部屋に来たな」と怒られた。ストレスもあったが、それ以上に得たものが多い。創業者らしいパワフルな章太会長と、熱意とともに知性を併せ持つ悠介社長の二人から「サラヤのDNA」を学べたからだ。
映画作家を夢見ながらタクシーを運転していた代島さんにとって、大阪での日々は新鮮だった。会社のフィロソフィと経営の両立。それを実現すべく奮闘する経営者親子。それは代島さんのドキュメンタリー魂を刺激した。代島さんは、サラヤという会社を、映像ではなく真実のドキュメンタリー「作品」にしたいと思った。

1950年代、石けん液を衛生的に供給する容器「押出・押上式」石けん容器を開発
世代交代。「世界を目指す」
2002年のサラヤ創業50周年。章太会長は完全に引退し悠介社長が仕切った。それは同社の世代交代についての象徴的なイベントになった。これまでは、天才肌の創業会長の陰に隠れる形になり、悠介社長が前面に立つことは少なかったからだ。
現社長の悠介氏は大阪大学の生物工学専攻。発酵や赤潮の研究をし、カリフォルニア大学バークレー校(UCB)で水質工学を学んだ。若い頃から「外に出たい」という意思を持っていた悠介さんは、UCBを出た後はアメリカで就職しようとした。しかし周囲の強い要望により日本に連れ戻された。日本に戻った悠介氏は「国際派」として、海外市場をゼロからとりにいく動きをした。
祐介氏はいつも父である創業者を立てて、気遣ってきた。50周年のイベントでは、その現社長が、全社員の前で初めて自分の考えを公言したのである。
「自分の代で成し遂げたいのは、サラヤを手洗いの世界トップ企業にすること」
創業者の章太氏と、現在の悠介社長の間で仕事をしてきた代島さんは、二人の経営者の関係をよく理解していた。代島さんは、悠介社長と一緒に、更家家の原点である紀州熊野にも何度も行っている。熊野川で、フライフィッシィングや鮎釣りもした。悠介社長が、自分の考えをしっかり持ちながらも、創業会長の顔を立ててきたこともわかっていた。だからこそ、50周年イベントでの悠介社長の言葉には深く感じるものがあった。

近年、香りつき洗剤が広がる一方で、その化学物質が引き起こす「香害」という言葉が生まれた。サラヤは無香料。それがフィロソフィ。
フィロソフィは永遠に
その10年後、東日本大震災の翌年にあたる2012年に、サラヤは創業60周年を迎えた。
60周年式典のなかで、更家悠介社長は、「創業者には感謝しかない」と深く頭を下げた。そして「サラヤは命をつなぐため、みなさんにお役に立ちます」と続けた。
代島さんもまた、同じ言葉を繰り返しながら、胸が熱くなった。
「あの震災で、サラヤは自らの役割を痛感しました。岩手、宮城、福島の三県を中心に、破壊された食品工場や急ごしらえの避難所など、衛生環境が命取りになる場所がたくさんあった。それで感染症の予防対策や衛生環境の回復に、全力で取り組みました。震災が起きてから洗浄液を生産しても、間に合いません。これまで持続的に生産してきたからこそ、いざというときに役立った。サラヤという会社は、こういう非常事態に対応するためにがんばってきた。サラヤの存在は、こういうときに人々を救うためにあったのかと、サラヤの存在意義を強く自覚し、身体が震えました」(代島取締役)」(代島取締役)
現在、更家悠介社長の思いとサラヤのフィロソフィを実現すべく、代島さんが中心となって、同社は社会貢献活動を積極的に展開している。2004年にボルネオの問題を知ったときも真っ先に現地に派遣されたのは代島さんだった。
代島さんは、具体的な数字を出して更家社長の成果を強調した。
「悠介さんが社長に就任した1998年、サラヤの売上は131億円でした。それが2016年には、サラヤ株式会社本体で350億円、東京サラヤ株式会社・およびスマイル産業株式会社を含む3社合計では408億円と、約20年で3倍。事業は拡大しても根底に流れているDNAは変わっていません」(代島取締役)
2015年1月31日、更家創業者の永眠後、密葬の儀を2月2日近親者にて執り行った。
出棺のとき、悠介社長から「代島さんも棺を担いでくれ」と言われた。「キミも、この人のおかげで、人生が変わった一人だろう」と。
棺を担ぎながら東京のタクシーの中で創業者と出会ったときからのことを思い出した。ドキュメンタリー作家を目指していた代島さんにとって、サラヤという「作品」に完成はないのかもしれない。

「地球は一つしかないので、どうするか。世界の持続可能性を考えなければならない」(更家悠介社長)
冒頭の2018年3月3日に行われた「第1回 日経ソーシャルビジネスコンテスト」において、登壇した更家社長は、受賞者に「みなさんの応援団になりたい」とエールを送った。
その言葉は、地球環境を、社会を良くしていこうと邁進しているサラヤ全社員へのエールであり、自ら世界各地に足を運び、地域にソーシャルビジネスの可能性を探っている自分自身に向けたエールでもあった。
「ビジョンが一致したら現地に飛びます。写真を観るより飛ぶほうがいい」(更家社長)
日焼けした更家社長の目が、持続可能な未来をみつめて輝いていた。

【企業情報】
社名:サラヤ株式会社
本社所在地:〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
創業 :1952年(昭和27年) /設立 1959年(昭和34年)
資本金:4,500万円
代表者 :代表取締役社長 更家悠介
事業内容 家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用品と薬液供給機器等の開発・製造・販売、食品衛生・環境衛生のコンサルティング、食品等の開発・製造・販売
参考文献
『これからのビジネスは「きれいごと」の実践でうまくいく』著:更家悠介著(2016年8月刊:東洋経済新報社)
『マルチチュード 上/下』著:アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート(2005年10月:NHKブックス)
取材後記
「次世代に伝えたい価値」を聞くことを、このサイトの記事の原則としている。更家悠介社長には、経営理念ないし事業コンセプトなどの「抽象的な概念」を期待していた。ところが、更家社長は「豊かな自然、清流のある環境そのもの」と答えた。取材後、その意味を考え続け、一つの結論に達した。サラヤにとってのフィロソフィ(哲学)は、目に見える「リアルな環境」そのものなのではないか。いくら美辞麗句を並べても、実際にビジネスの現場で成立しなければ、それは「ゼロ」のままだ。社長就任以来、「ゼロからイチ」を生む価値創造を続けてきたサラヤの社長だからこその言葉だったと、今もかみしめている。
取材・執筆:廣川州伸(ひろかわ くにのぶ)/コンサルタント、ビジネス作家
1955年9月東京生れ。都立大学人文学部教育学科卒業後、マーケティングリサーチ・広告制作会社を経て経営コンサルタントとして独立。合資会社コンセプトデザイン研究所を設立し、新事業プランニング活動を推進。東京工業大学大学院、独協大学、東北芸術工科大学などの非常勤講師を務め、現在、一般財団法人 WNI気象文化創造センター理事。主な著書に『週末作家入門』(講談社現代新書)『象を倒すアリ』(講談社)『世界のビジネス理論』(実業之日本社)『偏差値より挨拶を』(東京書籍)『絵でわかる孫子の兵法』(日本能率協会)など20冊以上。パズル作家としても著名で、地域を歩きながら魅力を発見する独自のパズル「謎解きクロス」を全国で展開している。
撮影:湧田佐恵子(わくた さえこ)/フォトグラファー。沖縄県生まれ、神戸市在住。
取材・構成:石原智/次世代価値コンソーシアム
掲載:2018年5月21日